2019年6月に行われた「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル」のセミナーに、一人の日本人女性が登壇した。広告会社でパラリンピックのプロジェクトに携わる木下舞耶さん。パラリンピックという障害者のスポーツの祭典を通じ、人々の意識、社会をも変えるコミュニケーションを標榜する。前編では、木下さんが歩んで来たこれまでの道のりを語ってもらった。





Photo=YUSUKE TAMURA (TRANSMEDIA)
2019年6月に行われた「カンヌライオンズ 国際クリエイティビティ・フェスティバル」のセミナーに、一人の日本人女性が登壇した。広告会社でパラリンピックのプロジェクトに携わる木下舞耶さん。パラリンピックという障害者のスポーツの祭典を通じ、人々の意識、社会をも変えるコミュニケーションを標榜する。前編では、木下さんが歩んで来たこれまでの道のりを語ってもらった。

Photo=YUSUKE TAMURA (TRANSMEDIA)
ーーどんな幼少時代を過ごしましたか?
日本人の父とアメリカ人の母のもと、アメリカのノースカロライナ州で生まれました。父の転勤でカリフォルニアに移り、小学校2年生のときに日本へ。大阪の学校に転入しました。
最初はカルチャーショックでした。方言に馴染みがなく、男子に「しばくぞ!」と言われたときも、「しばくって何?」と思いつつ怖くて学校を休んじゃったことも。でも、気がついたら自分もコテコテの関西弁でツッコんだりツッコまれたり(笑)。お笑いが好きで、友達とコントをつくって、クラスの男子と帰りの会でお笑いを発表したりしましたね。舞台に立つことも好きだったので、小5からは演劇部に所属しました。
高校時代の文化祭では、クラス劇の脚本・出演・演出と、全部やりました。1年生は「ルパン三世」、2年生はドラマ化される前の「電車男」を演劇に。3年生のときはブロードウェイ・ミュージカルの「キャッツ」の設定を借り、30分のオリジナルストーリーを創作。
「電車男」ではチャットの様子をスクリーンを使って表現するなど、今思うとすごくチャレンジングでイノベーティブなことをしていたなぁ、と。そのときは単純に楽しんでいましたね。
振り返ると、小学生のときのコントづくりも高校時代の演劇も、コピーライティングやストーリーテリングという今の仕事の「種」がそこにあったのかなと思います。とにかく人をエンターテインすることが好き。観た人に「おもしろい」と思ってもらえる何かを考え、パフォーマンスすることが本当に楽しいのです。それは昔も今も変わりません。
ーー卒業後はボストンの大学に留学しました。
正直、日本の大学や学部が自分に合っているかわからず、迷っていました。そんなとき、ニューヨークが舞台のウィル・スミス主演の「最後の恋の始め方」という映画を見て、NYええやん、アメリカええやん! って(笑)。母に伝えたら、アメリカの大学の学部が紹介されている本を渡してくれました。アルファベット順に紹介されていて、冒頭にあったのが「advertising」、広告コミュニケーションの学部でした。当時、iPodのCMがすごく流行っていて、CM自体とてもアイコニックだったし、商品も売れていた。クリエーティビティとビジネスが融合し、社会的に影響をもたらしているということに興味があったので、advertisingを学ぶ学部を探し始めました。
母の勧めもあって、ボストンの大学を受験。日本の大学センター試験のようなテストはあるのですが、テストの点数よりも、それまでの学校での成績や課外活動、そしてエッセイが重要視されます。「ボストンの中心地にある公園でなんでもできるとしたら?」という設問に対し、いろいろなカルチャーを融合させたお祭りをしてみたいというような企画を書きました。今考えると稚拙ですが、受験の時点で実践的なことを聞かれるという点が新鮮で、受けてよかったなと思いました。

Photo=YUSUKE TAMURA (TRANSMEDIA)
ーー大学の学びはいかがでしたか?
1年目は日本の大学同様、一般教養のクラスもあり、文化や哲学から、ジェンダー、ジャズなどの授業もあり、おもしろかったですね。とはいえ、基本的に日本の教育しか受けてこなかったので、「ペーパー」と呼ばれる小論文が書けず苦労しました。最初の授業で先生に「日本から来て慣れていないので、よろしくお願いします!」と伝え、常に最前列に座ってやる気と努力はアピールしました。ペーパーが悪くても「頑張ってるな」と思ってもらおうという作戦でもあったかな(笑)。
実際に広告会社で仕事をしていた講師も多く、街の中でのフィールドワークなど、実地に即した授業は本当におもしろかった。大学にはアートスクールも併設していて、寮の隣の部屋に住んでいた学生が制作していたコメディ番組の作品に出演したりも。普段できない体験ができたことは刺激的でした。
もう一つ、強く印象に残り、今の私に影響を与えたのがダイバーシティです。ボストンのあるマサチューセッツ州は同性婚が認められていることもあり、LGBTの人も多かった。それまでアメリカのドラマでしか知らなかったLGBTの人たちがごく普通に、オープンに暮らしていて、友達にもなった。
日本ではまだ一般的ではなかったけれど、私の中の見方がガラリと変わりました。同時に、社会的弱者である人たちをもっとサポートすべき、どんな人でも能力を発揮して幸せに暮らせる世の中であるべき、と考えるように。そもそもアメリカでは、日本から来た私もマイノリティ。強い人が全てを決める世の中は変えていかなければ、という思いを抱くようになりました。ちょうどアメリカでフェミニズム運動がSNSの力で若い人の間でもメジャー化し、大学でも白人が多い中マイノリティの採用に力を入れていたり、広告業界でも人種や性別のダイバーシティを活性化していこうという動きが出てきたりしていました。その流れは、きっと日本にいたら知ることも感じることもできなかった。
アメリカでの大学生活が、その後の人生観を変えたと言っても過言ではありません。そして、振り返れば今の仕事や仕事観にも大きな影響を与えることになるのです。

Photo=YUSUKE TAMURA (TRANSMEDIA)
ーー大学卒業後は?
できればアメリカで広告の仕事に就きたいとか思っていましたが、クリエーティブの仕事はポートフォリオ、つまり、自分が手がけた作品集がないと難しいのです。そんな中で受けたのが電通でした。日本の企業については偏った情報が多く、偏見を持っていたんです。でも、電通のパンフレットを見ておもしろそうだな、と。日本の企業というと忙しいイメージだったのですが、電通は「自分が興味を持っていることを自由に仕事にしていい」という社風でした。ここならやっていけるかも、と。卒業の翌年の2012年に入社しました。
ーー電通ではどんな仕事を? 仕事をする上で心がけていることはありますか?
クリエーティブ局に配属され、コピーライターに。コピーライターというとコピーを書く仕事、と思われがちですが、実際はCMプランニング、キャンペーンやイベントの企画といった業務も担当しています。
仕事をする上でのこだわりは、大きく二つあります。
一つは「ひと中心プランニング」。人が見てどう感じるか、どう行動するか、どう遊んでくれるかを想像すること。世に出して終わり、ではなく、受け手のその先までを考えるようにしています。人をおもしろがらせたい、心を動かしたいという気持ちは、子どものころから変わりません。クリエーティブは、あくまで人ありき、ということを常に心に置いて仕事に取り組んでいます。
二つ目は「広告は社会の鏡である」ということ。広告やマーケティングというのは社会の風景になる。たとえばかつて居酒屋には、水着姿の若い女性がジョッキを持ってニッコリ、というポスターが貼られていましたよね? 広告でそうした社会の風景を作ってしまうと、人々はいつまでも女性を性の対象物としか見なくなる。広告は社会を映し出す鏡であるんだ、という責任を引き受けて作らなければいけない。広告には、それだけの影響力がある。その力をいい形で社会の力にしていくことが、ブランドに共感するファンや仲間を作っていくことにつながりますし、ブランドや企業が社会に存在する意義が出てくると思うのです。
(後編に続く)
木下舞耶(株式会社電通 プランナー)
米国生まれ関西育ちのアメリ関西人。エマーソン大学卒業後、2012年電通入社。クリエーティブ局にてコピーライティングやCMプランニングを経験し、PRソリューション局へ。PR視点を取り入れたクリエイティブソリューションの開発やダイバーシティをテーマとしたプランニングを得意とする。
Cannes Lions、One Show、グッドデザイン賞、CMヒットメーカーランキング2019トップ10(CM総研)など受賞。

記者:中津海 麻子
慶応義塾大学法学部政治学科卒。朝日新聞契約ライター、編集プロダクションなどを経てフリーランスに。人物インタビュー、食、ワイン、日本酒、本、音楽、アンチエイジングなどの取材記事を、新聞、雑誌、ウェブマガジンに寄稿。主な媒体は、朝日新聞、朝日新聞デジタル&w、週刊朝日、AERAムック、ワイン王国、JALカード会員誌AGORA、「ethica(エシカ)~私によくて、世界にイイ。~ 」など。大のワンコ好き。
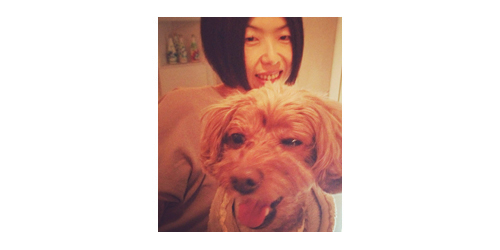
私によくて、世界にイイ。~ ethica(エシカ)~
http://www.ethica.jp






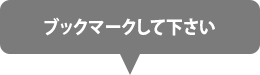
|
次の記事 |
|---|
|
前の記事 |
|---|
いいねしてethicaの最新記事をチェック
フォローしてethicaの最新情報をチェック
チャンネル登録して、ethica TVを視聴しよう
スマホのホーム画面に追加すれば
いつでもethicaに簡単アクセスできます

