現在、九州を中心に活動している陶芸家・古賀崇洋さんは作品の存在感を際立たせるために「反わびさび」という新しい概念を掲げ、器全体を大小のスタッズ(突起)で覆う派手でユニークなシリーズを展開、質素で静かなものをイメージする日本人の美意識「わびさび」とはかけ離れた作品を発表しています。


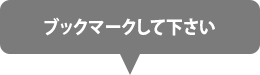
いいねしてethicaの最新記事をチェック
フォローしてethicaの最新情報をチェック
チャンネル登録して、ethica TVを視聴しよう
スマホのホーム画面に追加すれば
いつでもethicaに簡単アクセスできます